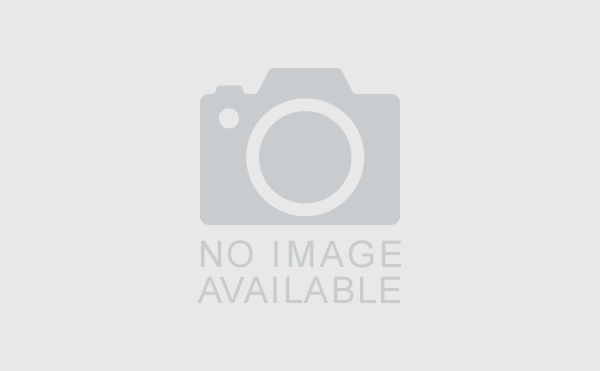塾生の声『小さな幸せ』(心の雨やどり)
このコーナーでは、季刊誌「パーセー」最新号より一部の記事を掲載 & 在塾生の感想をお届けします!
〈PerSe No.425 / 2025年 春季号〉より
心の雨やどり「小さな幸せ」
大越俊夫
このタイトルで書こうと思ってペンを執ると、ふと高倉健さんが主演した『幸福の黄色いハンカチ』(ずーっと前の映画です)を思い出しました。皆さん覚えていますか? 山田洋次さんが監督をして、倍賞千恵子さんが共演をして大ヒットしたソレです。ほのぼのとしたいい映画でした。そんな気分でペンを進めます。
時は九月末日、所は小清水原生花園のすぐ裏の海岸です。左右一面ずーっと砂地です。
小清水といってもピンときませんよね。北海道の地図を思い浮かべてください。右の上の方に北東に延びている細長い半島があるでしょう。そうそう、先端が世界遺産の知床の、あの半島のつけ根の北側、つまりオホーツク側の辺りが小清水なんです。
その砂浜の海岸に釣り竿を担いで五日連チャンで釣りに出かけたのです。この時期が秋アジ、俗称サーモン(鮭)のホットシーズンなんです。ピークは十月いっぱいですね。すでに肌寒いですが、目には紅葉でいうことなしです。
鮭を釣り竿で釣り上げるのは、慣れない人にはけっこう過酷な作業ですよ。それ程に巨大なんです。磯釣りの最高峰といってもいいでしょう。その作業を五日続けてやってごらんなさい。この歳の私でなくとも、若さの盛りの者でもキツイですよ。手足がバラバラな感じっていう感じ。そんな状態で机に座っています。身体はガタガタでも気分はいたって爽快。心が幸せだからです。そのワケをダラダラと綴ります。
舞台装置はおおよそ分かっていただきましたが、もう少しつけ足します。布製の真っ赤な大きなイスを砂地にドンと据え置いて、ドカンと座り、右を見ると何キロも何キロも砂地がつづき、大きく半円を描いて、遥か向こうに見えるのが知床連山です。一方、左側は、これまた砂地が延々とつづき、ゆるく右にカーブを描きその先端が網走です。海岸線沿いに車で走れば知床まで一時間、網走までは三十分かな、正面はオホーツクの海原、頭上は青空に白い雲が点々。頬にそよ風。太陽は真上です。これを舞台に、小さな幸せ劇が展開されたのです。
十メートル左で優介くんと清水くんが何やらバタバタし始めました。声は聞こえません。波に消されて、無声劇みたいです。釣れたのです、鮭が、優介くんに。必死に竿を曲げています。竿は半円を描き、上半身をうしろに反らそうとするが無理な感じ。清水くん、激励しながら、膝はすでに波の中。針先の獲物を蹴り上げるつもり。ヘルパーはみなそうするのです。つまり相互援助。ベテランは軽々と引き寄せますが、我々、素人はとうてい無理。私はどうするかって!? 私はベテラン中のベテランですよ。力不足はワザでといいたいところですが、大抵は若手がすぐに走り寄って来て砂地でバタバタしている鮭を蹴り上げてくれるんです。
優介くん、獲物の脳天を棍棒でポコン。仕留めたようです。二人とも両手を挙げて頭上で丸印。万円の笑み笑み! 無声劇、一幕終わり、という感じ。優介くんが獲物をぶら下げて近づいて来ました。大声を張り上げて、
優介:センセ、やりましたよ。釣りましたよ。やりましたよう。
私:スゲエ! やったなあ。よかったよかった。補佐役の清水くんまで嬉しそうです。彼らが近づいてハイタッチしようとした途端、今度は右側で竿を振っていた学(がく)くんが、ヨレヨレしています。竿先が海面に一直線、身体ごと海中に引きずり込まれそうです。それを巨体スタッフの金井くんが抱き止めて、何やら檄を飛ばしているふう。これまた無声劇です。悪戦苦闘。学くんの姿勢が正され、竿は半円を描き、アシストの金井くんが蹴り上げて落着。今度は、私が学くんの方に歩み寄って、
私:ついにやりましたね、学くん!
学:ハイ。やりました。凄かったです。びっくりしました。嬉しいです。とニヤリ。実は二人とも、今日が初釣果なんです。鮭釣りを始めて数日経つのですが、なかなかアタリもこず、やっとウキが沈んでもタイミングが合わずボウズ(釣れないこと)つづきでしたが、やっと今日、念願が叶ったというわけなんです。釣りをしない人にはピンときませんが、初釣果というのはなんとも嬉しいもんなんです。しかも、相手は磯釣りの最高峰、秋アジ(鮭)ですよ。この上ない釣りなんです。嬉しいなんてもんじゃありません。メジャーの大谷さんの50−50達成に匹敵するくらいの達成感なんです(少々、大袈裟)。
とにかくよかった。内心ヒヤヒヤしていた私も、これでひと安心で、心おきなく釣り竿を振れるというもんです。
三十歳になる優介くんの初釣果までの道のりは長かったですね。彼との初対面は十二年前かな。埼玉で生まれ育ち、バスケをしていた高校時代に監督とイザコザがあり、不登校。神経症に悩み、母親に付き添われて御影に引っ越し。不運なことに難病の潰瘍性大腸炎と診断され、諸事情を経て、今年の四月に母親と共に北海道・弟子屈町の我々の所に居を移し、今は塾生兼アシスタントとして日々を過ごすという状況。定期的に北見の病院に通い完治に励んでいる。お母さんは、地元の病院で老人介護に従事して、家計を支えているという状態。それなりに平和な日々ですが、綱渡り的な生活です。つまり、先の見えない生活の只中にあるという状況なんです。そんな中での鮭釣りなんです。普通なら笑ってなんておられませんよ。
アシストした清水くんは、ウチの正社員です。相棒と一緒にブルーベリー農園を作り上げ、時折、キッチンカーでパンを売り、コーヒーの焙煎にも精を出すというマルチスタッフです。
彼と出会ったのは十五年前。かつての東京校に入学して来ました。高一で不登校したとか。私と出会ってからは順調です。ウチの通信制高校(尾道)を卒業して、私が作ったプログラムでアメリカの大学に進み、学位を取って私の元に戻り、そのままずーっと側で活躍です。このような彼らの存在があって、我々の夢も前に進むというものです。
もともと今回の釣りは、清水くんの慰労のためだったのです。八月一日にブルーベリー農園が開園し、その準備や何やらで彼とゆっくり会う暇もなく、彼が釣り好きだと知っていたので声をかけ、塾生(北海道キャンパス生)の学くんが、札幌の専門学校のスクーリングで一週間頑張ったので声をかけ合い、巨体のチーフが面倒をみての釣行だというわけです。
二十歳の学くんと出会ったのは尾道の高校です。お兄さんが塾生だったせいで、彼が私のセミナーに初参加したのは、なんと四歳の時です。それからずーっと私の元で学んでいます。尾道、御影を経て去年の十月から弟子屈です。今は、スイーツ王子を目指して修行中ということです。
こんな連中とオホーツク海の海原で竿を振っているということなんです。今日で五回目ということは、毎回、誰かの慰労ということなんです。
私の身辺にはまだまだいっぱい若者がいますよ。加えて、元塾生のお母様方も居られます。九月二十日にオープンした摩周店でケーキを焼いておられます。今は多忙ですが、いずれ釣りにお誘いしようと企んでいます。
鮭釣りは十月からが本番です。よって、今は、前座です。手足がガタガタなどとほざいている暇はありません。青空の下で(時には大雨、暴風のことも)、右に知床、左に網走、正面にオホーツク海を舞台に、釣り劇は延々とつづくのです。加山雄三ではありませんが、「ボクは君と一緒に居る時が一番幸せなんだ」と口ずさみながらです。
小さな小さな幸せに包まれながら、釣り竿を振りつづけます。「お暇なら来てよね。私寂しいわ」と歌ったのは五月みどりさんだっけ。今年は間に合いませんが、来年は“お暇なら来てよね”です。
えっ? 釣った鮭はどうするのか? って。心配ご無用。発酵学者の小泉武夫先生のお知恵をお借りして、見事な「燻製」にして、皆様にお届けしますから。製品名は、「小さな幸せ」としますか!
では、また会いましょう。「さよなら、さよなら、さよなら」。
チャオ!
この記事に関する、在塾生の感想!
北海道キャンパス:篠原 祐翔このような文章を読むと、なんだか心が温まります。小清水の砂浜での秋鮭釣りの一幕。
目を閉じればその時の情景が鮮明に浮かぶような文章で、数ヶ月前のことがありありと思い出されます。
僕たちは全員が元不登校生です。年単位でひきこもり、釣りどころか外に出ることすらできないような状態でした。
人と話すこともできなかったし、体をまともに動かすこともできなかった。
それがダルボイ・アカデミーと出会い、大越塾長の元で癒しと遊びと学びをふんだんにいただき、元気を回復することができました。
大きなどん底を味わっているからこそ、同じ経験を共有している仲間たちと過ごす楽しい時間は、些細なことでも「小さな幸せ」なのです。
自分が釣れることよりも相手が釣れることで喜ぶ、相互援助で助け合う。
そういう話を聞いているとこちらもほっこりします。
まさに「喜び合うっていいなぁ」です。
この「喜び合うっていいなぁ」の空気がダルボイ・アカデミーには満ちています。
人の小さな幸せを喜び合うこと。これ自体が「小さな幸せ」なのだなぁとしみじみ感じます。
北海道キャンパス:大畑 壮史読んでいると、ほのぼのとした雰囲気を感じて、ほっとして幸せな気分になりました。
このほのぼのとした雰囲気はどこから生じているのか。
それは現代社会では薄くなった情があるからだと思います。
単なるビジネスだけでしたら、スタッフの慰労のために釣りに連れて行こうとはなりません。
釣った鮭を最後に仕留めるのは、釣った本人ではなくて周りにいる人です。
つまり、相互援助です。
ダルボイで釣りをするのは、釣りが好きというだけではなくて脳幹教育の一環として行っています。
現代社会は脳幹が弱りやすい環境なので、現代社会で生まれ育った塾生の脳幹を刺激して元気にしようということです。(詳しくは、大越俊夫著『子どもの脳幹が危ない!』幻冬舎)
塾生を元気にしようということも大越先生やスタッフの情を感じます。
合理主義や利己主義を超えた情を感じたので、ほのぼのとした雰囲気を感じてほっとして、幸せな気分になりました。
「心の雨やどり」に出てくる2匹の鮭は、釣りの神様からのプレゼントなのかもしれません。